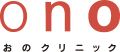2025.07.27
【在宅医療カレッジ札幌2025】「人口減少地域における在宅医療・緩和ケアの提供体制を考える」を聴講して
7月26日にオンライン(LIVE)で開催された【在宅医療カレッジ札幌2025】「人口減少地域における在宅医療・緩和ケアの提供体制を考える」を聴講した感想です。
「人口減少地域」、つまり、離島や僻地、発展途上国などでは、住民も医療専門職も、少ない資源、ある資源で、なんとかすることが必要になる。
「ないものはない!」と「腹をくくる」必要があるし、「覚悟」が必要となる。
一方、反対の都会、県・市の中心部では、医療・介護資源が豊富なので、「何かあったらどうしよう」「怖い、怖くてみれない」「責任もてません」…となり、医療を求め、医療にアクセスしたがる傾向がある(カンボジアも同様と)。
私も以前、元々当院かかりつけだった方が、介護施設でがんの末期となり弱って来られ往診したことがありました。そこは当院が連携している施設ではなかったけど、看護師さんがいる施設だったので、「ここの施設が好きで、皆さんにも愛されている。弱ってこられており、このまま衰弱されるはず。私も訪問するから最後まで看てあげて(看取って)」とお願いしましたが、その管理者でもある看護師は、「夜は看護師がいない。何かあったら責任持てない」と断固拒否され、結局、退所となり、入院となりました。
高齢者施設で、最後も近い方々ばかりなのに、ましてやがんの末期で、そのときも見えており、家族も納得していて、「避けないといけない死」ではないのに、「何かあっては…」「責任が取れない…」となる。住み慣れた場所から切り離し、入院させて何の意味があるのか?
一方、看護師がいない施設は、訪問看護が入らなくても、平気で(決して平気ではないのだろうけど)、人間の大きな、おおらかな「愛」(その人を愛おしむ気持ち)で、最後まで看取ってくれる。それと一緒だなと思いました。
ディスカッションでは、死や生などに関する住民の考え方を(医療介護の専門職種もだけど)、変えていかないといけない。
そういうものも一種の「文化」。文化も時代や状況と共に変わるし、変わる必要がある。
無駄な搬送、無駄な延命治療(本人が望まない)を減らすことで、医療費の高騰や、医療従事者の疲弊、モチベーション低下を減らせるはず。
住民には「覚悟」が必要なんだけど、一方で、「何かあったらどうしよう」の不安を和らげるのは在宅医療に関わる職種の役目でもある。
そもそも、医療介護専門職種の家族の最後は、どうなっているのか?
無駄のない医療を省く形、本人の思いに寄り添った(ACP)、本人らしい人生の最後を叶えてあげているのか?実際にはそうならなかったという話もよく聞くとのこと。
私は、3年前に、自宅で母を看取りました。妹(関東の大学病院看護師)が介護休暇を取りながら、自宅介護してくれました。素晴らしいことだな、普段、患者さん、家族、住民に色々と言っておりますが、実践できたなと改めて思いました。
周南市も、総人口は減り、高齢化率約33%(全国平均約29%)と高齢化も進んでいるし、診療所(開業医)も減少し、高齢化も進んでいます。
とても学び、気づきの多いシンポジウムでした。この学びを活かし、最後まで自分らしく、安心して暮らせる周南市を実現できるよう活動して参ります。